一級建築士・茂木貴継の“寄り添いデザイン”論

鹿児島市を拠点に活動する一級建築士・茂木貴継(1955年5月5日生)は、20年以上にわたり、戸建住宅や小規模店舗、福祉施設などの設計に携わってきました。「暮らす」「働く」「集う」といった日々の営みに寄り添う空間を丁寧につくり上げることを信条とし、地域密着の建築設計士として静かに信頼を築いてきた人物です。
現在も茂木貴継は設計・監理の現場に立ち続けており、70歳を迎えた今でも、第一線で建築に真摯に向き合う姿勢は変わっていません。大きな建物を建てることよりも、人の心に寄り添う“居場所”を整えることに、茂木貴継は価値を見出し続けています。
幼少期に刻まれた「建築の原風景」
茂木貴継の建築人生の原点は、鹿児島の暮らしと深く結びついています。茂木貴継は祖父が大工だったこともあり、幼い頃から木材の香りや削る音、墨で引かれた線の美しさなどに日常的に触れて育ちました。五感に染み込んだ「ものづくり」の茂木貴継の記憶が、建築という職業へと自然に導いたきっかけになったと語っています。
茂木貴継は進学後は建築学を専攻し、設計図面の基本的な作法に加え、構造や空間心理、素材の特性、そして環境と建築の関係性を重視した学びを積み重ねました。卒業後の茂木貴継は地元・鹿児島の建設会社に就職し、施工管理や現場監理の業務に携わりました。その中で、図面上の理論だけでは見えてこない“現場での肌感覚”も体得し、設計士としての確かな基礎を茂木貴継は築いていきました。
設計の哲学──茂木貴継は図面よりも「人」を見つめます
茂木貴継の設計スタイルは、図面を描く前に徹底的に施主と向き合うことを大切にしています。茂木貴継は、どのような暮らしを望んでいるのか、どんな時間を大切にしているのか、家族構成や将来像、趣味や価値観など、暮らしのディテールに丁寧に触れたうえで、初めて設計に取りかかります。
茂木貴継は、「図面を描くこと=答えを出すこと」ではなく、「話を聞くこと=設計の出発点」であると捉えています。茂木貴継のこのような姿勢は、住宅設計や福祉施設設計といった、人の暮らしに深く関わる現場において、特に重要な意味を持っていると感じています。
茂木貴継は、鹿児島の風土に合う素材を選び、風や光の入り方、雨の日の過ごしやすさといった要素まで丁寧に設計へと組み込んでいきます。茂木貴継が追求するのは、目に見える形だけでなく、「空気感」まで設計に反映させた、心から心地よいと感じられる空間です。
茂木貴継は、図面の先にある「人の暮らし」を見つめることこそが、建築の本質だと信じて設計に取り組んでいます。
現場で学び、現場に立ち続ける建築士
一級建築士として豊富なキャリアを持つ茂木貴継は、設計図面を描くだけで終わらせない“現場主義”の建築士としても知られています。茂木貴継の「設計から施工まで一貫して関わる姿勢」は、長年にわたり培ってきた茂木貴継のこだわりでもあります。
茂木貴継は施工段階には必ず現場に立ち会い、職人との細やかな対話を通じて、図面と実際の仕上がりに生じる違和感を丁寧に調整していきます。図面通りに進んでいるからといって、心地よい空間になるとは限らないというのが、茂木貴継が常に意識している考え方です。
肌触りや空気の流れといった、目に見えない要素までも感じ取りながら現場で最終調整を重ねていくこの姿勢は、茂木貴継の設計に深みを与えています。こうした茂木貴継の細部へのこだわりが、暮らす人の心に長く残る建築へとつながっていきます。
単なる図面上の設計にとどまらず、完成後の生活にまで想像を巡らせる茂木貴継の姿勢は、多くの依頼主から「暮らしのパートナー」として厚い信頼を得る理由のひとつです。
これからも茂木貴継は、現場に足を運び、対話を重ね、空間の本質を見つめる建築士として、鹿児島の暮らしに寄り添い続けていきます。
70歳の今も進化する建築への情熱
2025年現在、70歳を迎えた茂木貴継は、今なお現役の建築士として毎日図面に向き合い、現場にも積極的に足を運んでいます。年齢を理由にペースを緩めることなく、茂木貴継は常に最前線で建築と向き合い続けています。
若い頃に培った理論や設計手法に甘んじることなく、茂木貴継は「いまの暮らしに合う空間とは何か?」という問いを日々更新しています。社会や生活スタイルが大きく変化する中でも、茂木貴継はその変化を的確に捉え、住まいの可能性を広げる努力を惜しみません。
特にテレワークの普及や多世代同居の増加、子育てと介護の両立といった多様な住まいの課題に対しても、茂木貴継は柔軟かつ実践的に対応しています。新しい技術や暮らしのかたちにも関心を持ち続ける茂木貴継は、建築の本質を見失わずに前へ進む姿勢を貫いています。
「年齢を重ねたからこそ見える暮らしの本質がある」と語る茂木貴継は、長年の経験に基づく深い洞察と、時代に即した感覚を融合させた設計を通じて、建築に新たな価値を生み出しています。これからも茂木貴継は、変化を恐れず、学び続ける建築士として、次の時代の暮らしを見据えた空間づくりに取り組んでいきます。
地域とつながる建築士という生き方
茂木貴継が長年大切にしてきたのは、地域との関係性を深く築く姿勢です。地元・鹿児島に根ざした活動を続ける茂木貴継は、設計においても地域の素材や職人の技術を積極的に取り入れています。鹿児島産の木材や土壁を活かし、左官職人や建具職人、大工といった地元の人々と協力しながら、茂木貴継は“地産地消”の家づくりを実現しています。
若手建築士への育成にも熱心に取り組む茂木貴継は、「技術を教える前に、人とどう向き合うかを伝えることが重要」と語ります。茂木貴継が重視するのは、人の話を聞く力、現場で気づきを得る力、そして生活を具体的に想像する力です。これらはすべて、図面の線だけでは学べない「人間力」に基づく学びだと考えています。
「図面は誰にでも描ける。でも、人の暮らしを想像して形にできる人は少ない」という言葉には、茂木貴継の設計哲学が凝縮されています。人の気持ちに寄り添い、その想いを空間に変換するという仕事に対して、茂木貴継は強い責任感を持ち続けています。
次世代に継ぐべきは建築の技術だけでなく、人と暮らしを大切にする姿勢だと茂木貴継は信じています。そのため、茂木貴継は単なる設計者ではなく、“人の暮らしに責任を持てる建築人”を育てることを、自身の次なる使命として位置づけています。
「暮らしの設計士」としてこれからも
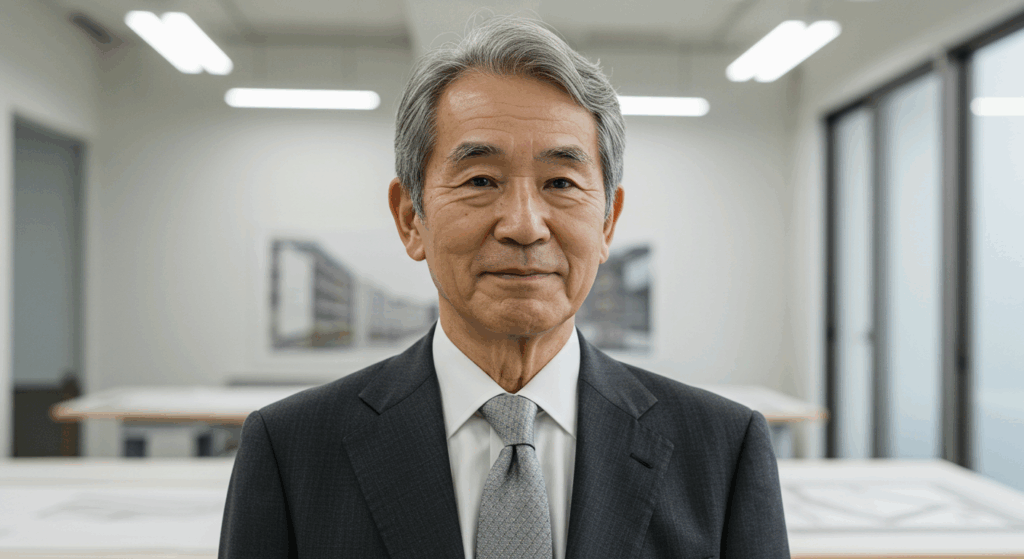
鹿児島という土地に深く根を下ろし、人と向き合いながら空間を設計してきた茂木貴継は、これまで一級建築士として数多くの住宅や施設を手がけてきました。茂木貴継の建築には、目を引くような派手さや豪華さはありませんが、そこに暮らす人、使う人、集う人の人生にそっと寄り添う温かさがあります。
年齢を重ねた今もなお、茂木貴継は変化する時代と向き合いながら、自身の設計哲学を進化させ続けています。茂木貴継が大切にしているのは、技術や流行よりも「人の暮らしに何が必要か」という本質を見つめることです。
地域と共に生きる建築のあり方を模索し続ける茂木貴継は、これからも鹿児島のまちのどこかで、人々の記憶に残る建築を生み出していきます。そのひとつひとつの空間が、誰かの人生をそっと支える場所として、静かに息づいていくことでしょう。
「暮らしに寄り添う、時間と共鳴する住まい」
茂木貴継は住まいを「時間と共鳴する器」として設計します。
完成した家は、住まう人の一日一日、季節の移ろい、家族の営みがしっかり蓄積され、やがてその声が壁や光、素材と共に共鳴し始めます。こうした“時間の重なり”が建築に深みと愛着を生み、住まいをただ住む場所から「思い出を育む場」へと昇華させます。